※当サイトのリンクには広告が含まれています。

【介護施設の電気代削減】新電力の選び方で失敗しないための完全ガイド
「毎月の電気代が経営を圧迫している」「コストは削減したいが、サービスの質は落とせない」。
多くの介護施設の運営者様が、このようなジレンマを抱えているのではないでしょうか。
特に24時間365日、利用者様のために稼働し続ける介護施設にとって、電気料金の高騰は無視できない深刻な経営課題です。
しかし、「電気代は変動するもので、対策は難しい」と諦める必要はありません。
この記事では、介護施設が直面する電気代の根本的な課題から、今注目されている「新電力」を活用した具体的なコスト削減方法、そして最も重要な「介護施設の新電力の選び方」で失敗しないためのポイントまで、専門家の視点から徹底的に解説します。
最後までお読みいただければ、貴施設の電気代に関する悩みを解消し、より安定的で質の高い施設運営を実現するための、確かな一歩を踏み出せるはずです。
なぜ今、多くの介護施設が電力会社の見直しを急いでいるのか?
近年、これまで以上に多くの介護施設が、契約する電力会社の見直しに真剣に取り組んでいます。
その背景には、単なるコスト意識の高まりだけではない、介護業界特有の切実な事情が存在します。
人件費や物価の上昇が続くなか、数少ない「コントロール可能な固定費」として、電気料金に注目が集まっているのです。
知らないと損!介護報酬改定が施設経営に与える本当の影響
介護施設の経営は、国の定める介護報酬に大きく左右されます。
定期的に行われる介護報酬改定は、施設の収入に直接的な影響を及ぼし、多くの事業者が改定のたびに収支計画の見直しを迫られます。
報酬が引き下げられる局面では、当然ながら利益が圧迫されます。
人件費はサービスの質に直結するため安易に削減できず、食材費などの物価も上昇傾向にあるなかで、経営努力だけで利益を確保するのは容易ではありません。
このような外部環境の変化に対応し、安定した経営を維持するためには、サービスの質を維持しつつ、管理可能なコストを徹底的に見直す必要があります。
その中でも、毎月必ず発生し、かつ削減の余地が大きい「電気代」という固定費の削減は、経営改善において非常に効果的かつ即効性のある手段となるのです。
電気代の高騰が運営コストを圧迫する2つの理由【燃料費調整額とは?】
近年の電気代高騰の主な原因は、大きく分けて2つあります。
一つは、火力発電の燃料となる原油や天然ガスの輸入価格の変動を電気料金に反映させる「燃料費調整額」の上昇です。
これは、海外からの燃料の仕入れ値が上がれば、私たちの電気代も自動的に上がるという仕組みです。
国際情勢の不安定化や為替の変動によって燃料価格が上がると、この燃料費調整額も上昇し、電気代全体が値上がりします。
もう一つは、太陽光などの再生可能エネルギーの普及を支えるために、すべての電気利用者が負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。
これらの要因は個々の施設の努力ではコントロールできず、以前と同じ量の電気を使っていても、請求額は年々増加する傾向にあります。
空調、照明、厨房設備、入浴設備、医療機器など、24時間体制で多くの設備を稼働させる必要がある介護施設にとって、この電気代の高騰は運営コストを直接圧迫する、非常に大きな要因となっているのです。
【経営改善事例】電気代の見直しで年間100万円以上のコスト削減に成功した事例
実際に電力会社を見直すことで、経営状況が大きく改善した介護施設は少なくありません。
例えば、ある中規模の介護施設では、従来の大手電力会社から新電力へ契約を切り替えただけで、年間の電気代を約100万円、削減率にして約15%も削減することに成功しました。
この削減によって生まれた資金は、老朽化していた入浴設備の更新や、職員の待遇改善のための賞与原資、さらには利用者様の満足度を高めるためのレクリエーション費用などに充てられ、施設全体の質の向上につながっています。また、別の小規模なデイサービス施設では、新電力への切り替えと同時に、施設内の照明をすべてLEDに交換。
これにより電気代が約30%も削減され、快適な環境を維持しつつ、大幅なコストダウンを実現しました。
このように、電力会社の見直しは、単なる経費削減に留まらず、より良い施設運営を実現するための戦略的な投資原資を生み出す、大きな可能性を秘めているのです。
引用:【介護でんきナビ(高圧電気)】
エリア別削減実績
| エリア | エリア料金 | 高圧フラットプランS | 7月分差異 | 削減率 |
| 北海道 | 843,746円 | 466,011円 | −377,735円 | −45% |
| 東北 | 1,035,495円 | 476,027円 | −559,468円 | −54% |
| 東京 | 695,822円 | 417,582円 | −278,240円 | −40% |
| 中部 | 653,682円 | 433,738円 | −219,945円 | −34% |
| 関西 | 545,703円 | 405,580円 | −140,123円 | −26% |
| 北陸 | 825,260円 | 408,381円 | −416,880円 | −51% |
| 四国 | 704,332円 | 410,007円 | −297,325円 | −42% |
| 中国 | 766,103円 | 408,588円 | −357,515円 | −47% |
| 九州 | 573,736円 | 415,031円 | −158,706円 | −28% |
※契約電力:200KW、使用量:30,000kWh、供給管理費:8.0 ※価格はすべて税込みです。
【基本】そもそも介護施設の「高圧電力」と「新電力」とは?

電力会社の見直しを検討する上で、まずは基本的な言葉の意味を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、「高圧電力」と「新電力」という2つのキーワードについて、専門的な内容をかみ砕いて分かりやすく解説します。
自施設はどっち?「高圧電力」と「低圧電力」の簡単な見分け方
電力の契約には、電気の使われ方の規模に応じて、主に「高圧電力」と「低圧電力」の2種類があります。
工場やオフィスビル、病院、そして多くの介護施設のように、たくさんの電気を一度に使う施設は、より効率的に電気を送れる「高圧電力」で契約しています。
一方、一般家庭や個人商店のような小規模な施設は「低圧電力」です。
自施設がどちらで契約しているかを確認する最も簡単な方法は、毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」を見ることです。
検針票の「ご契約種別」という欄に「高圧」という文字があれば高圧電力契約です。
この契約種別によって、選べる電力会社や料金プランが大きく変わってくるため、見直しを始める前に必ず最初に確認しましょう。
新電力に切り替えても電気の品質や安定供給は変わらない理由
「新電力に切り替えると、電気が不安定になったり、停電しやすくなったりしないの?」という不安の声をよく耳にしますが、その心配は全くありません。
新電力とは、2016年の電力小売全面自由化によって電力事業に参入した、大手電力会社以外の新しい電力会社のことです。
新電力会社に切り替えたとしても、実際に発電所から施設まで電気を届けるための電線や電柱といった「送配電網」は、これまでと同じ地域の大手電力会社のものを共同で利用します。
これは、高速道路に例えると「道路(送配電網)は今までと同じものを使い、料金所(電力会社)だけが変わる」ようなイメージです。
電気の通り道は変わらないため、供給される電気の品質や安定性、万が一の停電時の復旧対応なども、これまでと全く同じです。
料金プランやサービスだけが新しくなるとお考えください。
切り替えによる停電リスクの心配は不要です
電力会社を新電力に切り替えたことによって、停電のリスクが高まることは一切ありません。
前述の通り、送配電網の保守・管理は、引き続き地域の大手電力会社が法律に基づき責任を持って行います。
さらに、万が一、契約した新電力会社が倒産するようなことがあっても、国のセーフティネット制度(最終保障供給)により、電気が突然止まることはなく、地域の大手電力会社が自動的に供給を引き継ぐ仕組みになっています。
利用者は保護されているため、安心して自施設に最適な電力会社を選ぶことに集中してください。
【最重要】介護施設向け新電力選びで絶対に失敗しないための5つの比較ポイント
新電力会社は数多く存在し、それぞれに料金プランやサービスの特徴があります。
どの会社を選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。
ここでは、介護施設が新電力会社を選ぶ際に、絶対に確認すべき5つの重要な比較ポイントを、さらに深掘りして解説します。
ポイント1:料金プランは「固定単価」と「市場連動」のどちらを選ぶべき?
新電力の料金プランは、大きく「固定単価プラン」と「市場連動型プラン」に分けられます。
固定単価プランは、電気の使用量1kWhあたりの単価が契約期間中ずっと固定されているため、料金の見通しが立てやすいのが最大のメリットです。
一方、市場連動型プランは、日本卸電力取引所(JEPX)の市場価格に連動して料金単価が30分ごとに変動します。
市場価格が安い時間帯に電気を使えば料金を抑えられますが、猛暑や厳冬で電力需要が急増した際などに市場価格が高騰すると、逆に電気代が跳ね上がるリスクもあります。
24時間、常に一定の電力需要がある介護施設にとっては、毎月の支出が読みにくくなる市場連動型は経営上のリスクとなり得ます。
予算管理のしやすさと経営の安定性を考えれば、料金が安定している「固定単価プラン」の方が、安心して利用できるため断然おすすめです。
ポイント2:基本料金だけでなく「電力量料金」の内訳を必ずチェック
電気料金は、主に毎月定額でかかる「基本料金」と、電気の使用量に応じてかかる「電力量料金」の2つで構成されています。
見積もりを比較する際は、総額だけを見るのではなく、この2つの内訳をしっかり確認することが極めて重要です。
特に、空調や給湯などで電気使用量の多い介護施設では、電力量料金の単価が「1円」違うだけで、年間にすると数万円から数十万円もの差額になることも珍しくありません。
基本料金の安さに目を奪われず、自施設の年間の電気使用量と電力量料金単価を掛け合わせて、トータルでどちらが安くなるかを冷静に判断しましょう。
ポイント3:契約期間の縛りと「違約金」の有無を確認する方法
新電力会社の中には、1年や2年といった契約期間の縛りを設け、期間内に解約すると数万円から、場合によっては数十万円もの違約金が発生するプランもあります。
魅力的な料金プランであっても、将来的に施設の移転や統廃合、閉鎖の可能性がある場合、この違約金が思わぬ経営の足かせになることも考えられます。
契約を検討する際には、必ずウェブサイトの隅々まで確認するだけでなく、送られてくる契約書や重要事項説明書の「契約期間」「解約」に関する項目を熟読し、違約金の金額や発生条件を明確に確認しておくことが、将来のトラブルを避けるために不可欠です。
ポイント4:いざという時に助かる「支払い方法の柔軟性」
安定した施設運営のためには、日々のキャッシュフローの管理も生命線です。
特に介護事業は、国保連からの介護報酬の入金がサービス提供から約2ヶ月後になるなど、特有の入金サイクルがあります。
そのため、電力会社によっては、この入金サイクルを考慮して支払いサイト(請求から支払いまでの期間)の調整に応じてくれたり、万が一の際に支払い猶予の相談に乗ってくれたりする場合があります。
こうした柔軟な対応が可能かどうかは、資金繰りの安定性を支える上で見逃せない重要なポイントになります。
契約前に、支払いに関する条件やサポート体制についても具体的に確認しておくと、より安心して契約できるでしょう。
ポイント5:介護施設への導入実績とサポート体制の重要性
最後に、その新電力会社が介護施設への電力供給実績をどれだけ持っているかを確認しましょう。
多くの導入実績がある会社は、入浴や食事の準備で電力使用量が跳ね上がる時間帯など、介護施設特有の電力使用パターンや悩みを深く理解しており、データに基づいた的確なアドバイスや最適なプラン提案が期待できます。また、契約後の問い合わせや万が一のトラブルに、専門知識を持った担当者が迅速かつ丁寧に対応してくれるか、信頼できるサポート体制が整っているかも重要です。
会社の経営基盤の安定性も含め、長く安心して付き合えるパートナーとして信頼できる会社を選びましょう。
新電力への切り替え手続きは簡単3ステップ!申し込みから供給開始までの流れ
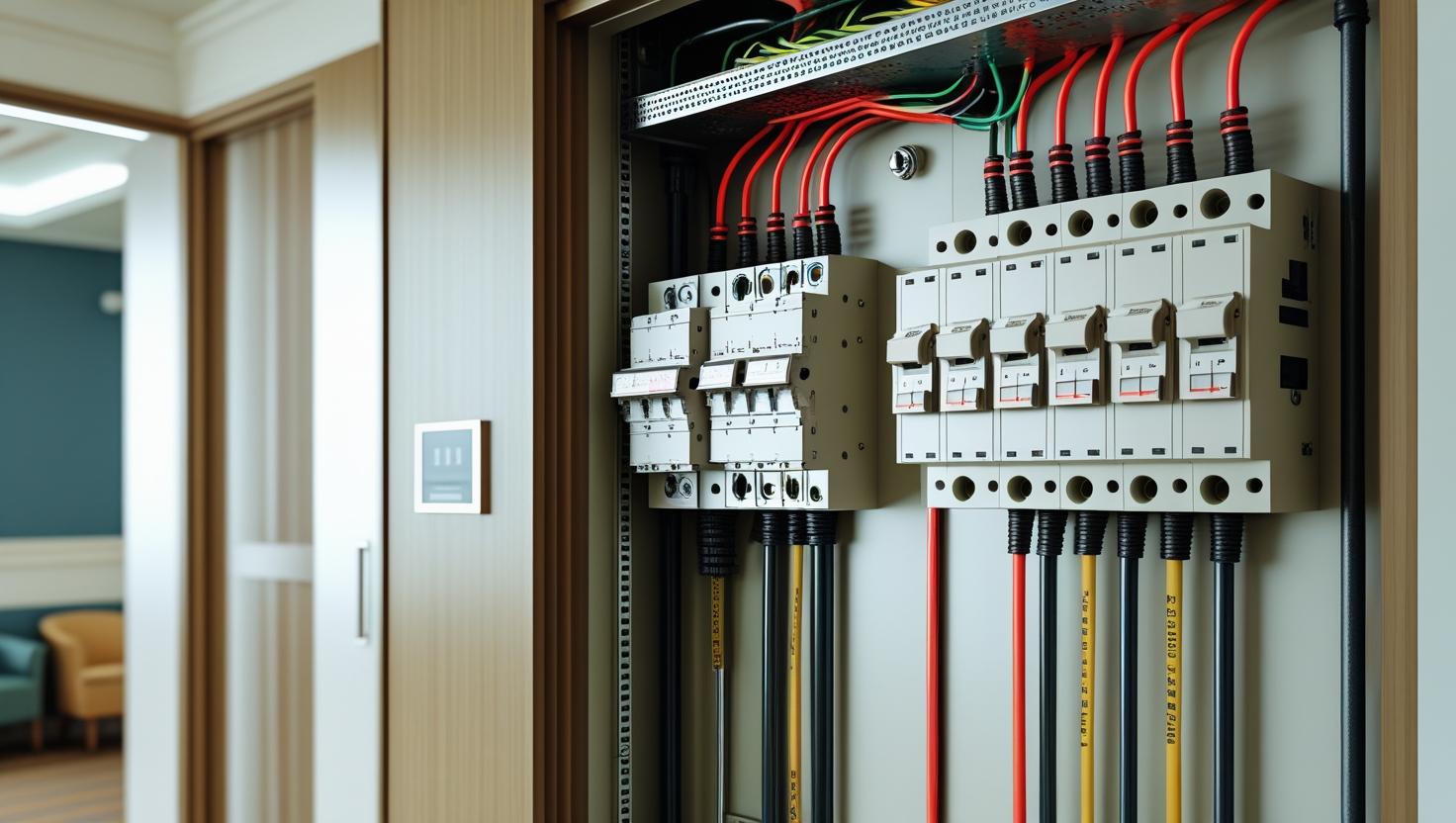
「電力会社の切り替えは、専門知識が必要で手続きが面倒で大変そう」と思われがちですが、実際には非常に簡単で、ほとんど手間がかかりません。
ここでは、申し込みから供給開始までの流れを、3つのステップでさらに具体的に分かりやすく説明します。
ステップ1:「検針票(電気ご使用量のお知らせ)」を用意する
まず、手元に現在契約している電力会社から毎月届く「検針票(電気ご使用量のお知らせ)」を準備します。
最適な料金プランの見積もりを出してもらうためには、過去1年分の電気使用量データが必要になるため、できれば直近12ヶ月分の検針票を用意すると、夏場の冷房や冬場の暖房による使用量の変動も考慮した、最も正確なシミュレーションが可能です。
検針票に記載されている「供給地点特定番号(22桁の数字)」や「お客さま番号」、「契約電力」といった情報が見積もりに必要となります。
ステップ2:複数の電力会社から見積もりと料金シミュレーションを取得
次に、用意した検針票の情報をもとに、気になる複数の新電力会社へ見積もりを依頼します。
多くの新電力会社は、ウェブサイトの専用フォームから検針票のデータを入力したり、写真をアップロードしたりするだけで、簡単に見積もり依頼ができます。
数日後には、無料で料金がどれくらい安くなるかの詳細なシミュレーションが提示されます。
このとき、必ず3社以上の会社から見積もりを取り、料金やサービス内容を多角的に比較検討することが、最も良い条件の会社を見つけるための絶対的なポイントです。
ステップ3:申し込みから供給開始までにかかる期間と注意点
比較検討して契約したい新電力会社が決まったら、ウェブや郵送で申し込み手続きに進みます。
申し込み手続きも、指示に従って情報を入力・記入するだけで完結することがほとんどです。
最も手間がかかると思われがちな、現在の電力会社への解約手続きは、新しく契約する新電力会社がすべて代行してくれます。
利用者側で行う作業は基本的にありません。申し込みから実際に電力が切り替わるまでの期間は、およそ1ヶ月から2ヶ月程度です。
切り替えに伴う特別な工事は原則不要で、切り替え作業当日に停電することもありませんので、日常業務への影響を心配することなく、安心して切り替え日を待つことができます。
介護施設の電力会社選びに関するよくある質問【Q&A】
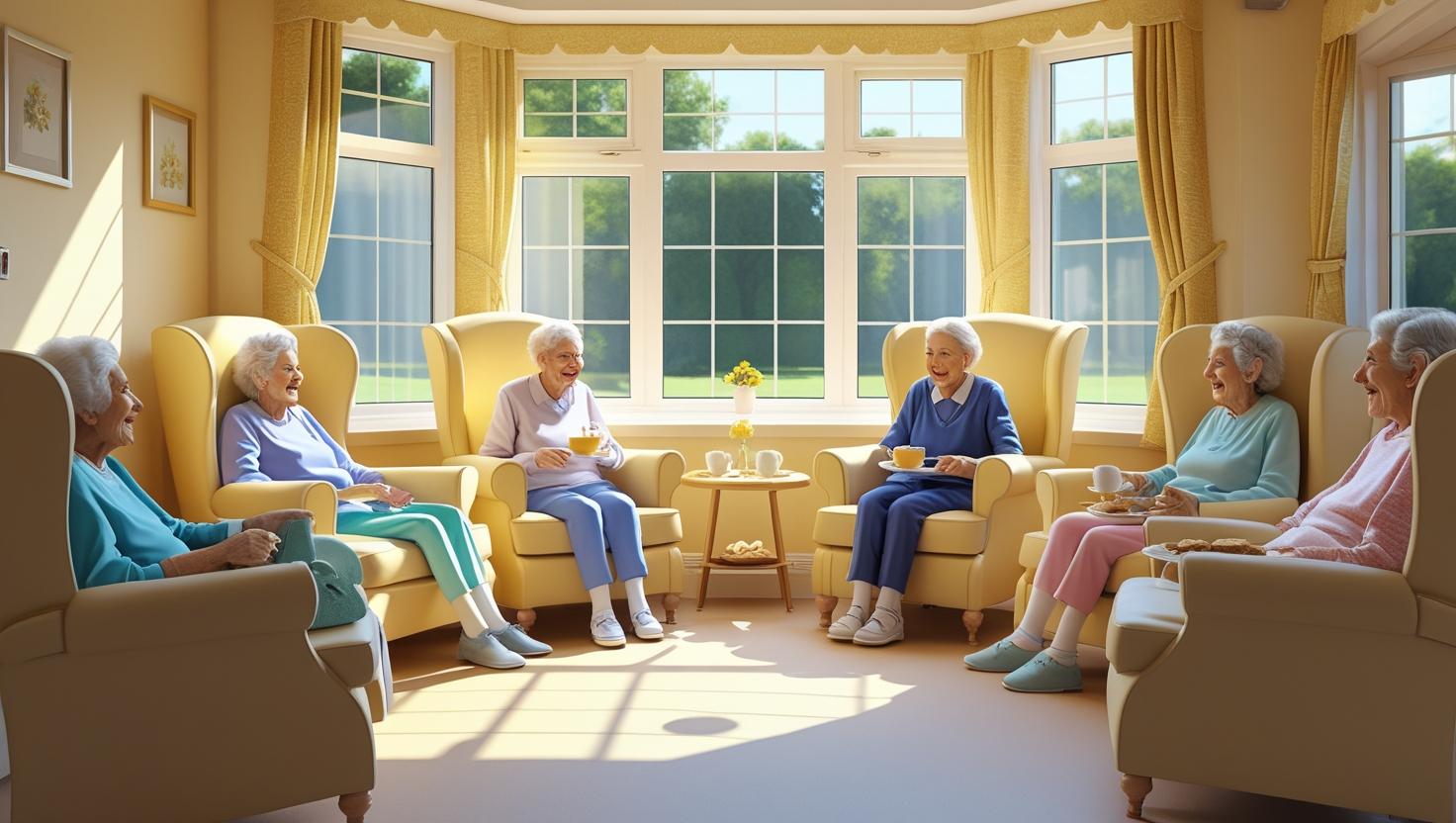
ここでは、介護施設の運営者様から特によく寄せられる、新電力への切り替えに関する質問とその回答をまとめました。
皆様が抱えるであろう疑問や不安を事前に解消し、安心して見直しを進めるためにお役立てください。
Q. 電力会社の切り替えに工事や初期費用はかかりますか?
A. いいえ、原則として特別な工事や初期費用はかかりません。
電力会社を切り替える際に、旧式の円盤が回るタイプの電力メーターから「スマートメーター」という新しいデジタル式のメーターへの交換が必要になる場合があります。
この交換作業は、地域の電力会社がその地域の全施設・家庭を対象に計画的に進めているもので、切り替えの有無にかかわらず実施されます。
作業は短時間で完了し、費用を請求されることは一切ありませんのでご安心ください。
Q. もし契約した新電力会社が倒産したら電気は止まる?
A. いいえ、絶対に電気が止まることはありません。
万が一、契約した新電力会社が倒産や事業撤退をしてしまった場合でも、電力の供給が即座に停止することはありません。
国の制度によって、地域の電力会社が一時的に電気の供給を引き継ぐ「最終保障供給」というセーフティネットが法律で定められています。
これにより、利用者は保護され、電気が使えなくなる心配はありません。
その間に、落ち着いて新しい電力会社を探して契約し直すことができます。
Q. 今の「市場連動型プラン」からすぐに乗り換えるべき?
A. 市場連動型プランは、電力市場の価格が高い時間帯に電気を使うと料金が大幅に高くなるリスクがあります。
特に、夏場の猛暑日や冬場の厳冬期など、電力需要が逼迫するタイミングでは価格が予測不能なほど高騰するケースも報告されています。
24時間安定して電気を使用する介護施設の場合、料金が予測しづらい市場連動型プランは経営リスクを著しく高める可能性があります。
毎月の電気代を安定させ、正確な予算管理を行うためには、料金単価が固定されているプランへの乗り換えを強くおすすめします。
Q. 支払いが厳しい月だけ「支払い猶予」をお願いすることは可能?
A. これは契約する新電力会社の規定や方針によります。
会社によっては、事前に相談することで支払い期限の延長などの相談に柔軟に応じてくれる場合があります。
特に介護施設向けのプランを提供している会社は、業界の資金繰りの特性を理解している可能性が高いです。
キャッシュフローの安定は施設運営において非常に重要ですので、契約を検討する段階で、そうした支払いに関する柔軟な対応が可能かどうかをサポート窓口などに具体的に確認しておくと、いざという時に大きな安心材料になります。
まとめ:最適な新電力選びが介護施設の未来を明るくする
ここまで解説してきたように、介護施設が電力会社を見直し、新電力を賢く選ぶことは、単なる経費削減以上の大きな意味を持ちます。
それは、施設の持続可能性を高め、より良いサービスを提供し続けるための、極めて戦略的な経営判断なのです。
5つの比較ポイントを元に自施設に合った電力会社を見つけよう
料金プランの種類、料金の内訳、契約条件、支払い方法の柔軟性、そして導入実績とサポート体制。
この5つの重要な比較ポイントをチェックリストとして活用し、複数の会社を丁寧に比較検討することで、貴施設にとって本当に最適な電力会社が必ず見つかります。
目先の料金の安さだけでなく、施設の状況を理解し、長期的に安心して付き合えるパートナーを選ぶという視点が、成功の鍵を握ります。
専門家への相談がコスト削減への一番の近道
数多くの新電力会社の中から、自力で最適な一社を見つけ出し、各社の複雑な見積もりを比較検討するのは、多忙な業務の合間に行うには大変な時間と手間がかかります。
そのような時は、ぜひ電力の専門家にご相談ください。
多くの施設の事例を知る専門家であれば、貴施設の詳細な電力使用状況を分析した上で、最も効果的なプランを客観的な視点から提案することが可能です。
プロの力を借りることが、結果的に時間と労力を節約し、コスト削減を最大化する一番の近道となります。
まずは無料の料金シミュレーションで削減額を確認してみませんか?
電力会社の見直しは、もはや一部の施設が行う特別なことではありません。
物価が高騰し続ける現代において、安定した経営基盤を築き、利用者様と職員にとってより良い環境を提供し続けるための、賢明な経営判断の一つです。
まずは、現在の電気料金がどれくらい安くなる可能性があるのか、無料の料金シミュレーションでそのポテンシャルを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
その具体的な削減額が、貴施設の明るい未来を照らす、確かな第一歩となるはずです。
